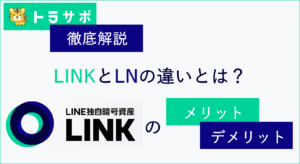DeFi(ディーファイ)ってよく聞くけど、これまでの仮想通貨とどこが違うの?
ここでは、イマイチ理解が難しく感じるDeFiについて、詳しく解説する。

英単語の意味は、分散型金融
本質の意味は、銀行や証券会社に頼らずに金融機能を実現する
DeFiではこういった取引所を通さない違いがある
目次
- 1 DeFiにはさまざまなプロジェクト(サービス)がある
- 2 DeFiが持つリスクやデメリット
- 3 なぜDeFiは世界中で注目されているのか?
- 4 DeFiをよく知る上で必携のキーワード
- 4.1 DeFi必携キーワード①:DEX(分散型取引所)
- 4.2 DeFi必携キーワード②:Uniswap(ユニスワップ)
- 4.3 DeFi必携キーワード③:PancakeSwap(パンケーキスワップ)
- 4.4 DeFi必携キーワード④:レンディングプラットフォーム
- 4.5 DeFi必携キーワード⑤:イールドファーミング
- 4.6 DeFi必携キーワード⑥:流動性マイニング
- 4.7 DeFi必携キーワード⑦:ステーブルコイン
- 4.8 DeFi必携キーワード⑧:Maker(メイカー)
- 4.9 DeFi必携キーワード⑨:WBTC
- 4.10 DeFi必携キーワード⑩:予測市場
- 4.11 DeFi必携キーワード⑪:コンポーザビリティ(マネーロゴ)
- 4.12 DeFi必携キーワード⑫:Compound(コンパウンド)
- 5 種類別!DeFiの具体的な稼ぎ方を解説
DeFiにはさまざまなプロジェクト(サービス)がある
DeFiは分散型金融のサービスの総称であり、資産の預入・貸し借り・投資など、さまざまなサービスが利用できる。
「プロジェクト」や「サービス」に接続して利用する。
たとえば、暗号資産を取引したい場合は「Uniswap」や「PancakeSwap」などの分散型取引所に接続する。
資金を借りたいなら「Compound」などのレンディングプラットフォームに接続すればよい。
2020年6月、DeFiが盛り上がった「コンパウンド」プロジェクト
DeFi市場が急激に盛り上がりを見せたのは、2020年6月のことだ。
「Compound」(コンパウンド)が、プロジェクトの意思決定に介入するための権利(ガバナンストークン)を配布した。
Compoundは、DeFiを利用するプロジェクトの一つで、非常に人気が高い。
Compoundの大幅値上がりを受けて、他のDeFiプロジェクトもガバナンストークンを続々発行するようになった。銘柄によっては、30倍近く価格が高騰している。。
このように、非常に高い利益を生む市場としてDeFiは投資家から大きな注目を集め、2020年に利用者が急増した。バブルのようだったが、2021年8月現在、価格は落ち着いている。
とはいえ、DeFiの仕組みは新しい金融サービスの形なので、今後も投資先として期待されるだろう。
DeFiで大きな利益が得られた事例
分散型暗号資産取引所の「Uniswap」は、2020年9月1日より前にUniswapで取引をしたことのあるユーザーに対し、一律400UNIトークンを配布した。
配布された当時の売却レートは3ドル前後だったので、Uniswap利用者は最低でも1200ドルを獲得できたことになる。
また、古くから流動性を提供(資産を預け入れ)しているユーザーに対しては、より多くのトークンを配布した。そのため、ユーザーの中には1億円以上の資産を獲得した人もいた。
このようなUniswapの事例は、あくまで特殊なケースだろう。しかし、DeFiプロジェクトは新しいサービスが続々とローンチしている。
バイナンスなどの取引所に上場する前に、将来性の高いプロジェクトに投資してトークンを入手しておけば、このようなチャンスに巡り会えるかもしれない。
これによって、DeFiに興味を持つ人が大きく増えた。
DeFiが持つリスクやデメリット
DeFiには、もちろんデメリットもある。
新しい金融システムなので、特に利用者保護とシステムの観点にリスクを抱えている。
リスク①:資産が消失してしまう
DeFiは新しい仕組みのため、まだ信頼に足る実績がない。

銀行や証券会社、保険会社といった、従来の中央集権型金融システムでは、明確な制度や法律が整備されている。そのため、金融システム側の問題で損失が発生しても、補填される可能性が高かった。
だが、DeFiでは、日本のみならず各国とも制度や法律の整備が追いついていない。利用者保護の仕組みがないため、資産の消失リスクが常に付きまとう。
リスク②「ラグプル」などの詐欺が多発している
DeFiに資金が集まるにつれて犯罪も増加している。その中でも多いのが「ラグプル」(Rug pull)や「スキャム」(scam)と呼ばれる詐欺だ。
たとえば、2021年3月に起きた「NFTP」というサービスに関わる事件だ。このサービスは、Pancakeswapとの関連を匂わせ、「今がチャンス」「億り人になれるかも」などといった買いを煽るツイートが連投され、1日で価格が急騰した。
しかし、その日の深夜に大暴落し、運営元のサイトは跡形もなくなっていた。このように、DeFiプロジェクトの開発者が偽のプロジェクトを作って資金を集め、高騰したところでサイトを閉鎖して持ち逃げする詐欺が非常に多い。
2020年の仮想通貨詐欺では、DeFiのラグプルが大半を占めており、新しい情報に飛びついたら詐欺だったということも少なくない。このような詐欺から身を守るには、自身が詐欺かどうかを見抜く一定のリテラシーが必要となる。
リスク③取引にかかる費用(通称:ガス代)が高騰している問題
DeFiに関する取引が増えるに連れ、イーサリアムブロックチェーンで、データを記録するための費用(通称:ガス代)が高騰している。
イーサリアムのガス代は、高い金額を払った人から優先的に処理がされる。そのため、ガス代を安く抑えようとすると、中々処理が行われない。
DeFiの多くはイーサリアムブロックチェーンを利用しているため、まさに今、ガス代の高騰という問題に直面している。
DeFiの実現に必要な「スマートコントラクト」という機能がある。スマートコントラクトはNFTでも使われている

そうなれば、ガス代も常識的な価格で落ち着くようになるはず。
なぜDeFiは世界中で注目されているのか?

暗号資産で資産を運用している場合、取引所に預けた状態でチャートをチェックして一喜一憂している人が多いだろう。
一時期の暗号資産バブルのような状態ならともかく、ある程度落ち着いてきた現状では、暗号資産を保有しているだけではより多くの運用益が見込めない。そこで、一歩踏み込んで運用したいと考えた人の間で話題となったのがDeFiだった。
DeFiが注目を集めている理由は、まったく新しい金融の仕組みであること、そして何より常識を外れた運用益にある。このような運用益を得られるのは、DeFiがまったく新しい仕組みを持っているからだ。
DeFiが注目されるようになった理由をまとめよう。
金融業者が関わらないのでリスクが高い代わりにリターンが大きい

従来の金融システムは手数料が高い
これまで、お金の預け入れや貸し借り、株式への投資、保険への加入といった金融サービスを利用するには、銀行や証券会社、生命保険会社などの金融業者を使う必要があった。
このような従来の金融業者は、人を雇ったりオフィスを借りたりするためのコストが必要だ。このコストをどこで賄っているかというと、利用者への手数料ということになる。
たとえば、銀行でお金を借りれば利子が発生するが、これには金融業者への手数料が上乗せされている。これ以外にも、ATMからお金を引き出す際に取られる手数料、株式投資で生まれた運用益に対する仲介手数料など、さまざまな手数料を利用者が負担しなければならなかった。
DeFiでは手数料が下がる
DeFiの登場によってこの状況は一変する。DeFiはブロックチェーン上に構築されているため銀行のような中央集権的な組織が存在せず、すべての取引がスマートコントラクトで自動的に行われる。
そのため、人件費や土地代といったコストが発生しないので、その分のコストが利用者に還元される。今まで無駄な手数料を払っていた感じている人にとっては嬉しい話だろう。
DeFiをよく知る上で必携のキーワード

実は、DeFiは、色々なサービスを組み合わせて実現されている。
そのため、DeFiでは多くのキーワードが登場する。これらのキーワードを知っていると、DeFiをより詳しく理解できることだろう。
DeFi必携キーワード①:DEX(分散型取引所)
「DEX」(デックス)は「Decentralized Exchange」の略で、分散型暗号資産取引所のこと。
中央管理者が存在しない暗号資産取引所のことを指す。
中央管理者がおらず、スマートコントラクトで自動決済され、取引記録はすべてブロックチェーン上で記録・管理される。
資産を預けておくウォレットはユーザー自身が管理するのが特徴だ。
暗号資産取引所には、DEX(分散型取引所)とCEX(中央集権取引所)の2種類があり、次のように分類できる。
DEX(分散型取引所)とCEX(中央集権取引所)の違い
| DEX | CEX | |
| 種類 | 分散型暗号資産取引所 | 中央集権型暗号資産取引所 |
| 管理者 | 無し | 有り |
| 本人確認 | 不要 | 必要 |
| 資産の保管場所 | ユーザー自身のウォレットに保管 | 取引所が管理 |
| 取引されている通貨数 | 5〜10000種類 | 5〜100種類 |
| 取引方法 | AMM (一部で板取引) |
板取引 |
| 代表的な取引所 | Uniswap PancakeSwap Curve Finance など |
Coincheck GMOコイン Binance など |
表は右にスクロールできます

板取引とAMMって何?
DEXのメリット
DEXのメリットには「セキュリティが高い」点が挙げられる。
CEXの場合、ユーザーの資産は取引所内のウォレットで管理する。
そのため、安全対策はCEXの運営会社に委ねられてしまう。もし、CEXがハッキングの被害に遭ったら、資産を失う恐れもある。実際にハッキングによる資産の盗難などの被害が発生している。
DEXの場合、ブロックチェーン上に構築されているため、ブロックチェーンに侵入して情報を直接改善しなければならない。これは事実上不可能に近い。万が一、ブロックチェーンがハッキングされたとしても、自分が管理するウォレットはハッキングされることはない。
これ以外のDEXのメリットとして、取り扱っている暗号資産が豊富な点がある。国内の代表的なCEXである「Coincheck」で扱う暗号資産は約20種類であるのに対し、DEXを代表する取引所の「Uniswap」では約4000種類以上にも上る。
また、DEXは中央管理者がいないので、本人確認の必要がなく、すぐに利用を開始できるメリットもある。
ただしデメリットも少なくない。DEXはイーサリアム上に構築されていることが多く、その利用には手数料(ガス代)がかかる。現在、イーサリアムの手数料は高騰しており、DEXの取引の手数料も急騰中だ。
DEXには中央管理者が存在しないため、サポートが受けられないという点もある。たとえば、操作がわからない場合、CEXならサポートセンターでサポートを受けられるが、DEXにはそういったサポートが一切ない。また、秘密鍵がわからなくなったり、送信先を間違ってしまったような場合のサポートもなく、すべて自己責任となる。
また、これはDEXに限ったことではないが、DeFiには詐欺サイトが多く存在する。これは、DeFiプロジェクトはオープンソースのため、誰でもコピーしてサイトを立ち上げられてしまうのが原因だ。詐欺に引っかかっても補償は受けられないので、詐欺サイトに引っかからないように利用者自身が注意するしかない。
DeFi必携キーワード②:Uniswap(ユニスワップ)
「Uniswap」(ユニスワップ)とは、分散型暗号資産取引所のひとつ。
イーサリアムブロックチェーンに構築されており、イーサリアム上では最も使われているDEXだ。
2018年から運営が行われており、仮想通貨の取り扱いは1500種類以上だ。Uniswapでは、資金を預け入れると専用ガバナンストークンである「UNI」を報酬として獲得できる。
UniSwapが既存のDEXと異なる点は、どんな暗号資産も上場できるところだ。
暗号資産は、「ETH」と「ERC20トークン」の組み合わせなら追加できる。使い道のない暗号資産を預け入れれば、手数料収入につなげられるメリットがある。
DeFi必携キーワード③:PancakeSwap(パンケーキスワップ)
「PancakeSwap」(パンケーキスワップ)とは、分散型暗号資産取引所のひとつ。
海外の大手取引所バイナンスが出資している分散型暗号資産取引所で、BSC(Binance Smart Chain)に構築されている。
2021年2月時点で24時間の取引高が2000億円を超えており、分散型暗号資産取引所としては上位に入る。
Pancakeswapに資金を預け入れると、専用ガバナンストークンである「CAKE」を報酬として獲得できる。ユニークなのは宝くじ機能で、CAKEトークンを10単位以上保有するユーザーには賞金があたる可能性がある。
バイナンスのBSCとは?
BSCとは、世界最大の暗号資産取引所「バイナンス」が構築したブロックチェーンで、イーサリアムブロックチェーンに比べて手数料が圧倒的に安いのが特徴。つまり、PancakeSwapは手数料が非常に安いというメリットがある。
DeFi必携キーワード④:レンディングプラットフォーム
レンディングプラットフォームとは、管理者不在で預金・貸付を行うサービスのことを指す。DeFiレンディングプラットフォームは、貸し手と借り手をスマートコントラクトの技術を使って結びつけ、低い手数料で暗号資産の貸し借りを可能にする。
仕組みは、資産を貸したい人がイーサリアムなどの暗号資産をプールし、借りたい人が賃借料を払って暗号資産を借りていく。ここで借り手が支払う金利手数料を、貸し手が利息として受け取ることができる。従来だと、利息は仲介者に手数料として徴収されていたが、レンディングプラットフォームは徴収されることなく利息を得ることができる。
借り手は、個人情報やクレジットカードの信用情報がなくても、イーサリアムを担保に資金を調達できるメリットがある。
DeFiでの代表的なレンディングプラットフォームに、Compound(コンパウンド)、Arve(アーヴ)、バイナンスローンなどがある。
DeFi必携キーワード⑤:イールドファーミング
「イールドファーミング」とは、Defi上のサービスに暗号資産を預け、流動性を提供する見返りに金利や手数料収入がもらえる運用モデルのこと。「イールド」は「利回り」、「ファーム」は「耕す」を意味している。
DEXやレンディングプラットフォームなどでは、プールに十分な資産を預け入れられていないと取引が成立しない恐れがある。そのため、資産を預ける(流動性を供給する)ユーザーは、報酬として利息が与えられる。この利息で利益を得ることがイールドファーミングだ。
イールドファーミングのすごいところは利回りの高さにある。次に説明する流動性マイニングを組み合わせることにより、年利数十〜数千%を超える利益を生み出すことが可能になった。この圧倒的な利回りで、投資家から大きな注目を集めている。
DeFi必携キーワード⑥:流動性マイニング
「流動性マイニング」は、イールドファーミングに新たに加わったテクニックで、イールドファーミングの報酬で得たトークンをさらにまた預けることによって利益を生み出す手法だ。
たとえば、PancakeSwapの場合、流動性を提供すると手数料収入以外に、「CAKEトークン」を獲得できる。このCAKEトークンで流動性を提供すれば、さらにCAKEトークンを獲得できる。
流動性マイニングは、このようにトークンがトークンを生み出す錬金術のようなものだ。
この流動性マイニングの仕組みで多くの資産を呼び込み、トークンの価値が向上した。高い利回りを獲得できるようになり、DeFiは大きな注目を集めることになった。つまり、流動性マイニングに多くの新規ユーザーを呼び込んだといえる。
DeFi必携キーワード⑦:ステーブルコイン
ステーブルコインとは、安定した価格を実現するように設計された通貨のことだ。ビットコインなどの暗号資産は、円やドルなどの法定通貨と比較すると価格変動が激しくリスクが大きい。
ステーブルコインは法定通貨や特定の仮想通貨を担保することにより、安定した価格を実現することが可能になる。
ステーブルコインは、価格を安定させる手法により次の3種類に分類できる。
ステーブルコインの3つの区分
| 区分 | 説明 |
| 法定通貨担保型 | ドルや円といった法定通貨を担保にしたステーブルコイン。 法定通貨との交換比率を固定化することで、価格を安定化させている。 |
| 仮想通貨担保型 | 特定の暗号資産を担保にしたステーブルコイン。暗号資産は価格が不安定なため、安定化を実現するために担保とする暗号資産を2倍に増やすなどしている。 |
| 無担保型 | 法定通貨や仮想通貨などを担保とせず、コインの供給量を調整することで法定通貨と同様の値動きを目指すステーブルコイン。 |
DeFi必携キーワード⑧:Maker(メイカー)
「Maker」(メイカー)とは、「DAI」(ダイ)というステーブルコインの発行や管理するDiFiプロジェクトだ。

「DAI」は、仮想通貨担保型のステーブルコインで、イーサリアムの仮想通貨「イーサ」(ETH)を担保にし、米ドル(USD)と価値を紐付けるステープルコインを発行・保有することができる。
なお、2019年11月以降、イーサリアム以外にベーシック・アテンション・トークン(BAT)が担保資産に加えられ、複数の仮想通貨を担保にDAIが発行されるようになった。
DAIを生成することにより、米ドルとの交換レートが制限されていたり、そもそも口座が作れないといった制約を受けている利用者でも、ネット上で米ドルと同等の価値を持つ通貨を取引できるようになる。
DeFi必携キーワード⑨:WBTC
WBTCは「Wrapped Bitcoin」の略で、仮想通貨担保型ステーブルコインの一種。ビットコインと価格が連動しており、トークン規格である「ERC20」に準拠しているのが大きな特徴だ。
ビットコインは、独自のブロックチェーンを持つ暗号資産のため、そのままではDeFiで運用することができない。しかし、DeFiで運用するために含み益を抱えたビットコインを売却したくないということもある。
このようなニーズに対応しているのがWBTCだ。つまり、WBTCはDeFiでビットコインを利用するために使われるものと考えていいだろう。
WBTCの発行は「カストディ型」と呼ばれる方法で、BitGO社が現物のBTCを預かり、WBTCを発行する。また、これ以外では、WBTCを扱っている取引所で購入するという方法もある。
DeFi必携キーワード⑩:予測市場
予測市場は、ある特定の将来を予測してお金を儲けるための市場のこと。たとえば、選挙の当選結果やオリンピックの結果などを予測してお金を賭けるときに使われる。DeFiの予測市場プロジェクトでは、予測が的中すると、スマートコントラクトによって自動的に報酬が付与される仕組みだ。
分散型の予測市場は、プログラミング化されていることにより外部から影響を与える要素が少ないのが特徴。公の機関による圧力や汚職による不正が少ないサービスだ。
ただし、予測市場はギャンブル性が高く、DEXやレンディングプラットフォームなどと比べると普及のペースが遅い。
予測市場の代表的なDeFiプロジェクトとして、「Augur」(オーガー)、「Omen」(オーメン)、「Polymarket」(ポリマーケット)などがある。
DeFi必携キーワード⑪:コンポーザビリティ(マネーロゴ)
DeFiのサービスは、いずれもブロックチェーン上で動くプログラムなので、相互に連携させてより便利にサービスを利用できるようにすることが容易だ。この複数のDeFiサービスを組み合わせて新しいサービスを作り出すことを「コンポーザビリティ」や「マネーレゴ」と呼ぶ。
代表的なコンポーザビリティは、インド発の「インスタダップ」(Instadapp)だ。インスタダップでは、Uniswap、Maker、Compound、Arveなど、各種DeFiサービスを直接利用できる。
また、レンディングプラットフォームのCompoundとArveの利率をチェックして、より高い方に自動的に資産を貸し出す「インスタブリッジ」という機能も有している。
DeFi必携キーワード⑫:Compound(コンパウンド)
「Compound」(コンパウンド)は、DeFiで提供されるレンディングプラットフォームのひとつ。イーサリアムブロックチェーンに構築されており、イーサリアム上では最も使われているサービスだ。
Compoundで貸し借りを行うと、「COMP」と呼ばれるガバナンストークンを獲得できる。獲得できる量は利益や利息の額によって変わってくるので、多く獲得したい場合は利益率の高いものを選ぶ必要がある。なお、COMPトークンはBinanceに上場したことで価値が高まっており、資産としても非常に魅力的なトークンになっている。
また、預け入れられる資産は、暗号資産だけでなくステーブルコインも可能。暗号資産は価格の変動リスクがあるが、価格が安定しているステーブルコインで運用すれば、変動リスクを抑えて着実に収益を上げることが可能になる。
たとえば、「DAI」の場合は年利6%以上とかなり高額に設定されているので、確実に収益を上げたい人にはおすすめだ。
種類別!DeFiの具体的な稼ぎ方を解説
実際にDeFiではどのように稼げばいいのか。ここでは以下の3つの方法を解説するよ。
DeFiの稼ぎ方①:レンディングプラットフォームに預けて利息収入を狙う

レンディングプラットフォームでは、お金の貸し手は預けた通貨に対して利息を獲得できる。銀行にお金を預けておくと利子が付くのと同じような原理なので、DeFi初心者の人でもわかりやすい仕組みだろう。当座の運用予定のない暗号資産を持っているなら、預けておくといいだろう。
レンディングプラットフォームに預け入れた場合の年利は、通貨によって異なってくる。Compoundの場合、通貨に対する年利は次の通りだ(2021年8月現在)。
Compoundに対する通貨の年利一覧
| 通貨名 | 年利 |
| DAI | 2.51% |
| ETH | 0.18% |
| UNI | 0.18% |
| USDC | 2.57% |
| WBTC | 0.46% |
| USDT | 3.03% |
この表の通り、年利はあまり高くはない。ただ、日本の銀行のような「0.001%」のような年利と比較すれば十分に高額だ。通貨の値上がりによる利益が得られないが、純粋に年利のみで収益を上げたいという人にはちょうどよい投資方法だろう。
また、Compoundで貸し借りをたくさんすれば「COMPトークン」を獲得できる。このトークンはバイナンスにも上場され、高値をつけているので、年利以上の利益を生む可能性があるのもポイントだ。
DeFiの稼ぎ方②:流動性を提供する「プール」という仕組みで手軽に利益を得られる
DEXでは、プールに資産が豊富に蓄えられていないと取引が成立しない恐れがある。そのため、ユーザーがプールに資産を預けると、利回り報酬以外の報酬が与えられる仕組みになっている。
このときに与えられる報酬が、取引所のガバナンストークンだ。このトークンは資産としての価値を持つだけでなく、トークンをプールに預け入れることにより、より高い利回りで運用できるようになる。
元々DEXもCEX(中央集権型取引所)と同様に板形式を用いた売買が取り入れられていた。板形式の場合、ユーザーの希望価格を一覧にし、売り手と買い手の双方が売買価格に合意したら取引が成立する。
しかし、イーサリアム上にあるDEXでこの形式を使うと、価格交渉のやり取りのたびに手数料(ガス代)が発生してしまい、取引を成立するまでにかなりのコストがかかってしまう。このような理由により、利用の頻度は決して多くなく、資産の流動性が低くて遅いという欠陥を抱えていた。
これを解決するために作られたのが「プール」という仕組みである。ユーザーがプールに資産を預け入れれば、その報酬としてガバナンストークンを獲得できる。この報酬を得るためにプールが利用され、それにより流動性が高まり、取引の利便性が飛躍的に高まった。DeFiが爆発的に成長したのは、この報酬がもらえる仕組みが大きな一因だろう。

プールの仕組みだが、2つのトークンをペアで預けることで即時に取引を実現している。貸し手は2つのトークンをプールに預け入れる。借り手は自身の保有するトークンをプールに加えることにより、借りたいトークン引き出せる。
この際、借り手が加えるトークンに手数料が若干上乗せされている。この手数料分が、貸し手にガバナンストークンという形で分配される。
この取引はAMMで自動的に行われるので、プール内に十分な流動性があれば瞬時に取引が成立する。
プールした場合の年利は非常に高いのが魅力
プールすることにより得られる金利収入は非常に高いのが大きな魅力だ。
PancakeSwapの場合、さまざまな通貨で組み合わせて預け入れられる。たとえば、「CAKE/BNB」や「BUSD/BNB」といった組み合わせの場合、これらの年利は「CAKE/BNB」では54.94%、「BUSD/BNB」でも27.95%だ(2021年8月現在)。預け入れしてしまえば、あとは待つだけ。しばらく時間が経つとトークンが増えていくはずだ。

インパーマネントロスの例
| 通貨ペア | 年利 |
| USDC/BUSD | 10% |
| USDC/USDT | 10.76% |
| ETH/USDC | 26% |

このように、仕組み自体は複雑そうに見えるが、運用自体は非常に簡単なのがポイント。取っつきにくそうだが、実際にやってみるとそれほど難しくなく高い利益が狙える。
DeFiが注目を集めている理由の1つだ。
DeFiの稼ぎ方③:DeiFi関連の仮想通貨銘柄で数百~数千%のリターン可能性!?

DeFiでは、DEXやレンディングプラットフォームが配布しているガバナンストークンの多くが取引所で売買されている。このトークンの中には急激な値上がりを見せているものも多いので、そのような銘柄を保有できれば、大きな利益を獲得できることになる。
2020年11月から2021年2月までの間、価格が高騰した代表的な銘柄には次のようなものがある。
DeFi関連で高騰した仮想通貨の例
| 通貨名 | 変動率(年利) |
| Uniswap | 約+1200% |
| COMP | 約+700% |
| CAKE | 約+6300% |

このようにDeiFi関連銘柄は非常に高騰していることがわかる。上記の銘柄は代表的なもので、他にも多くのDeFi関連銘柄が取引されている。
特に狙い目なのが、バイナンスなどに上場していない将来性のある銘柄だ。ここで大きく伸びる銘柄に投資すれば、より多くの利益を獲得できるだろう。
仮想通貨の場合、年利は「購入したコインの枚数」が対象となる。つまり、年利100%の場合、100万円が200万円になるというわけではなく、購入したコインが100枚なら200枚になるという意味だ。そのため、コイン価格によっては金額も変わってくる可能性がある。