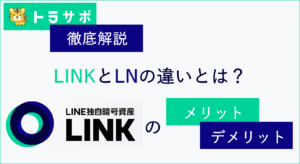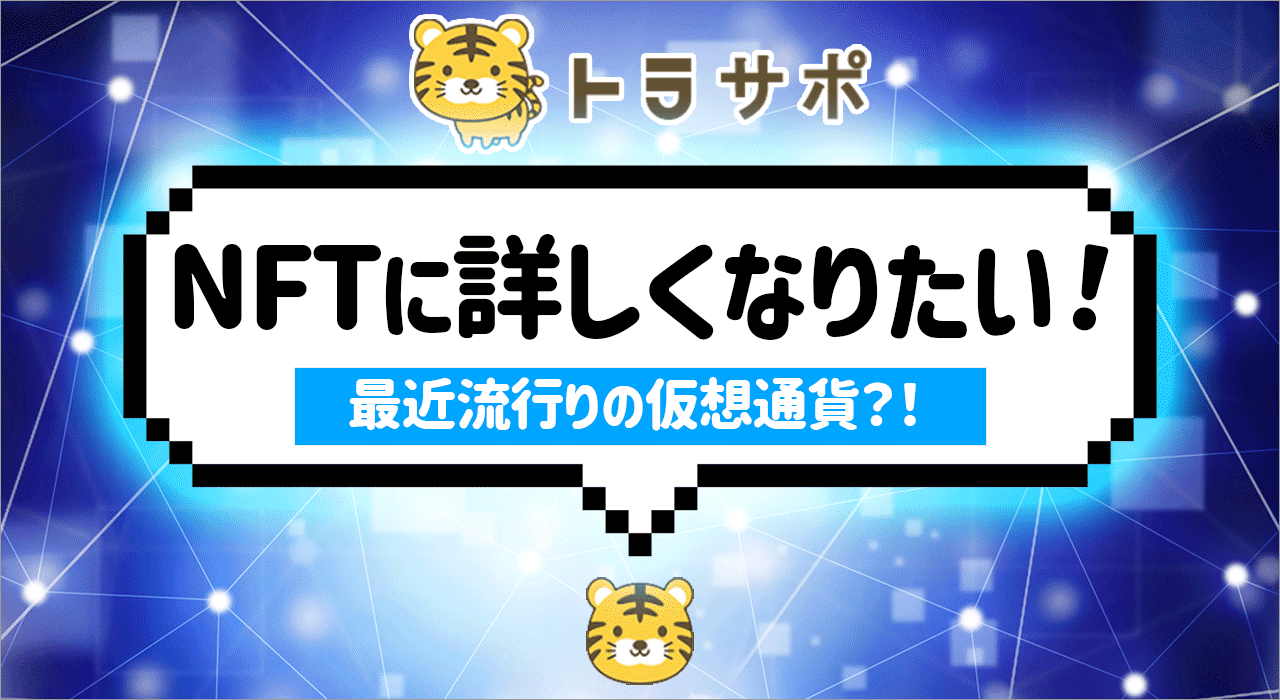

パソコンで作った写真・イラスト・動画などのデジタルデータは、コピーし放題。
そのため、デジタルデータには、絵画や不動産のように現物としての資産価値を認めるのが難しい。
デジタルデータに対して、資産価値を認めるにはどうしたらよいだろうか。その答えの1つとして登場したのが「ブロックチェーン」。
しかし、改ざんされにくいだけでは、デジタルデータのコピー防止には不十分だ。例えば、デジタルデータのイラストがあったとしよう。
デジタルデータをコピーすれば、オリジナルとコピーではどちらが「本物」か見分けることは不可能だ。

NFTでデジタルデータが「本物」かどうかがわかる
そこで登場したのがNFT(Non Fungible Token)だ。「Non Fungible」は「代替不可能」という意味で、デジタルデータに「偽造不可能な鑑定書・所有証明書」(メタデータ)を追加するもので、デジダルデータが「本物」であることを証明する。

暗号資産やセキュリティトークンと、NFTとの違いは?
暗号資産やセキュリティトークンは代替可能
暗号資産やセキュリティトークンは「代替が可能なトークン」だ。たとえば、Aさんが持っている1万円札をBさんが持っている1万円札と交換しても何も問題はない。つまり「代替が可能」なのだ。
暗号資産やセキュリティトークンもこれと同じで、あくまで「○○円分の資産価値を持ったデジタルデータ」として扱われる。そのため、他の暗号資産や現金と交換することができる。
NFTは代替不可能で、唯一無二な存在
一方、NFTは、デジタルデータごとにメタデータが紐付いている。データそのものをコピーしてもメタデータまでは、コピーできない。
つまり、NFT化されたデジタルデータは「唯一無二」なものだ。

NFT化されたデータは世界に1つしかないことが証明されるので、いくらコピーされてもオリジナルのデータを「本物」として認定できる。
このように、唯一無二なものとして扱えるNFTは、さまざまな用途への活用が模索されている。
・音楽
・ライブチケット
・ゲームのアイテム
NFTと暗号資産やセキュリティトークンでは規格も異なる
NFTの大半は、イーサリアムブロックチェーン上で取引されている。
イーサリアムにはERC(Ethereum Request for Comments)というトークン規格があり、NFTと暗号資産では規格が異なる。
どのように規格が異なるのか、NFTと暗号資産やセキュリティトークンの違いも併せて、以下の表にまとめた。
NFTと暗号資産やセキュリティトークンの違い
| 名称 | NFT | 暗号資産(仮想通貨) | セキュリティトークン |
| イーサリアムでの規格 | ERC721 | ERC20 | ERC1400 |
| 代替できるか | 不可 | 可能 | 可能 |
| 分割できるか | 不可 | 可能 | 可能 |
| 主な使用用途 | デジタルアート/楽曲/ゲーム/仮想空間上の不動産など | 仮想通貨などの数量的なもの | 各国の金融法を遵守した株式や債券などの資産 |
なお、現在のNFT取引はイーサリアムブロックチェーンが主流となっているが、他のブロックチェーンも取り扱うものが増えてきた。今後はブロックチェーン間での競争が激しくなっていくだろう。
NFTと暗号資産やセキュリティトークンは取引の方法も大きく異なる
暗号資産の取引方法
暗号資産の取引は「暗号資産交換取引所」で行う。代表的な取引所に「Coincheck(コインチェック)」や「GMOコイン」などがある。
取引を始めるには、暗号資産交換取引所で口座を開設し、日本円を入金する。あとは取引したい暗号資産を売買すればよい。
多くの取引所はスマホのアプリが用意されており、これを使って手軽に取引が可能だ。
セキュリティトークンの取引方法
セキュリティトークンは、発行する組織などが投資家に直接トークンを販売できないため、現状では個人が取引することは難しい。
だが、SBIホールディングスがSTO事業への取り組みを開始している。2023年をめどにセキュリティトークンの取引所が設立される予定だ。
NFTの取引方法
NFTは「NFTマーケットプレイス」で取引を行う。NFTの取引を始めるには、まず決済で使う暗号資産を入手する。
暗号資産はイーサリアムを使うことが多いので、暗号資産交換取引所でイーサリアムをあらかじめ入手しておく。
次に、NFT売買用の暗号通貨を保管する「ウォレット」を作成し、ウォレットに暗号資産を送金する。最後に「NFTマーケットプレイス」でアカウントを発行すれば準備が完了だ。
- NFT化されたデジタルデータは、コピーとオリジナルを区別できる
- デジタルアートや音楽、ライブのチケット、ゲームのアイテムなどがNFTに向く
- 現在、NFTはイーサリアムブロックチェーンで取引されることが多い
- NFTを取引するには、暗号資産(主にイーサリアム)、ウォレット、NFTマーケットプレイスのアカウントが必要になる
なぜNFTは突然大ブームになったのか?

最初はゲーム内のアイテム売買に使われた
最初にNFTが注目を集めたのは、2017年のことだった。「CryptoKitties」というゲームがイーサリアム上で誕生した。
このゲームで使われるキャラクターが、ゲーム内のマーケットプレイスで販売できるようになった。そして、「ドラゴン」と名付けられた珍しいキャラクターが約1900万円で売買され、話題となった。
しかし、ゲーム内のアイテム売買だったため、一般の人の目に留まることはなく、それ以上に盛り上がることなく、ブームは沈静化した。
暗号資産が高騰し、NFTが注目を集めた
2020年の暗号資産の高騰が、そのきっかけだ。Paypalが暗号資産業界への参入を表明してから、暗号資産全体が値上がりした。
これにより、ビットコインの所有者は莫大な資産を手に入れたが、利益を確定(円やドルなどの法定通貨に交換)してしまうと高額な税金が発生してしまう。そこで注目を集めたのがNFTだ。
ビットコインなど暗号資産を法定通貨に交換するのではなく、NFTに替えて持っておけば、税金はかかりにくい。
Twitter創業者のジャック・ドーシーのツイートが高額で落札された

引用元:Twitter
VRアーティストのせきぐちあいみ氏の作品は約1300万円で

国内では、VRアーティストのせきぐちあいみ氏の作品が約1300万円で落札された。
NFT登場前は、デジタルデータに資産価値をつけるのは難しかった。しかし、NFTによって売買市場が形成され、資産価値が生じて、アート界隈で注目を集めるようになった。
ここで紹介したような高額での取引が実際に行われたことが、一般の人からも急速に注目を集めた理由のひとつだろう。
さらに、NFTは個人でも比較的容易に始められ、NFT化したデジタルデータを販売することも可能だ。NFT化できるデータの種類も多く、希少価値を生み出せる。これもブームの一因になっていそう。
- NFTによってデジタルデータに資産価値が生じた
- NFTは個人でも始めやすく、対応可能なデータの種類も多い
- ビットコインなど暗号資産の値上がりで、資産の逃げ場所となった
NFTが持つデジタル機能とは何か?
NFTは新しい価値の可能性を生み出した。
NFTは、デジタルデータに新たな価値を与え、ユーザーにさまざまな恩恵をもたらすと言われている。
- デジタルデータに希少価値を与える
- 暗号資産の垣根を超えた自由な取引が可能に
- 個人でも自由にデジタルデータを作成・流通できる
- 転売など二次流通でも制作者へ利益が還元される
ブロックチェーンで「代替不可能なもの」を証明でき、希少価値が生まれる
1つ目のポイントは、NFTを用いることでブロックチェーン上で流通するデジタルデータに唯一の価値を持たせることができる(オリジナルとコピーを区別できる)という点だ。
NFT化されたデジタルデータには、所有者などのメタ情報が付加される。これにより、改ざん困難なブロックチェーン上で表示されたNFTデータは、他のデジタルデータと区別可能な唯一の存在として扱われる。
あらゆるデジタルデータでオリジナルとコピーを区別できるので、著名なアーティストやクリエイターにとっては、NFTによる恩恵は非常に大きい。もちろん、それ以外の一般ユーザーにとって希少価値の高いものをNFT化すれば、大きな利益が見込まれる。
Dapps間でデジタルデータを自由に取引できる
2つ目のポイントは、共通のプラットフォームで作られたDapps内なら、デジタルデータの移動が可能になる点だ。
Dappsは「decentralized applications」の略称で、「中央管理者なしに提供されるアプリケーション」(自律分散型アプリケーション)のことだ。一般的に、暗号資産ゲームのことをDappsと呼ぶことが多い。
このDapps上では、NFT化されたデジタルデータを別のDappsに移動させることが可能になる。
Dappsでの取引例
Dappsを利用すると、ゲームAで入手したアイテムをゲームBでも使用できたり、アイテムを暗号資産に交換(売買)できたりする。
実際にはゲームバランスの問題などもあり、現在対応しているゲームは一部だけだ。だが、ゲーム同士のコラボなどで活用されれば、新しいゲームの世界が開けるだろう。
誰でもデジタルコンテンツを作って流通できる
誰でもデジタルコンテンツを作成して流通できるのもポイント。
NFT化できるアイテムのジャンルは幅広い。具体的には、次のようなものがNFTに向いている。
- イラストやグラフィック、動画などのアート作品
- ゲームのアイテム
- 仮想空間上の土地
- SNSの投稿
- ドメイン
- 電子書籍や音楽
現在、上に挙げたもの以外にも、どのようなコンテンツがNFTによる流通に向いているか、世界中の人が繰り返し実験しているところだ。まだまだ新しいビジネスチャンスが転がっていると言えるだろう。
転売しても制作者に利益が生まれる
NFTがなければ、コンテンツが転売されたとき、制作者には利益は発生しない。しかし、NFTが設定されていれば、転売時に制作者にも利益が生じる。
NFT化されたコンテンツなら、転売時に制作者へ利益が発生するように「転売フィー」を設定できる。つまり、NFTデータが転売されても、制作者に利益が生まれる。
- 唯一無二を照明することで、デジタルデータに希少価値が生まれる
- Dappsを使ってデジタルデータを自由に取引できる
- 誰でもコンテンツを流通できるので新しいビジネスチャンスが生まれる
- コンテンツが転売されても制作者に利益が生まれる
NFTのメリット・デメリット
ここまで説明してきたように、NFT化されたデジタルデータはオリジナルとコピーが区別でき、唯一無二のものとして扱える。
そのため、デジタルデータに資産価値が生まれ、注目を集めることになった。
だが、メリットばかりではない。NFTは新しく開発された技術なので、指摘されている問題点やリスクも少なくない。
- 著作権を所有していると誤解してしまう
- 著作権者以外の第三者がデジタルデータをNFT化できる
- 「ガス代」が高騰している
- NFTデータの価値がなくなる
- コンプライアンス基準が未整備である
著作権を所有していると誤解してしまう
デジタルデータ(コンテンツ)の著作権は制作者にある。NFTを所有していても、コンテンツの著作権まで保有していることにはならない。つまり、ブロックチェーン上での所有者(NFTの所有者)と著作権者は全くの別物だ。
そのため、NFT所有者は、著作権者が持っている著作物の複製・販売する権利、著作権自体を譲渡する権利、二次的著作物を作成する権利などを通常所有していない。
NFT所有者と著作権者は同じ意味ではない
たとえば、著作権者がデジタルアートをNFT化して販売した場合を考えよう。
NFTを購入した人は正当なNFT所有者となり、第三者に対して「所有者」という権利を主張できる。
だが、所有者が「著作権も所有している」と勘違いしてデジタルアートを他人にコピーして渡したり、SNSなどでそのデータを共有したりした場合、著作権上の問題が発生する。
NFTで保護されるのはメタデータのみ
NFTで偽造できないのは「鑑定書・所有証明書」にあたるメタデータの部分だけだ。コンテンツ自体はコピーできてしまう。そのため、コンテンツがネットに流出することは防げない。
著作権者以外の第三者がNFT化できる
NFTは誰でも手軽に作成できる。これを悪用して、コンテンツの著作権を持っていないのに関わらず、NFTを販売できるという問題がある。
実際、現状では著作権を持たない第三者が、例えばディズニーのキャラクターをNFT化して販売することも可能だ。
法的な問題も見過ごせない
NFTが新しい技術であることも、問題を複雑にする。
もし、著作権侵害で裁判になった場合、NFTに関する判例がほぼないため、判決に至るまで時間がかかる可能性が高い。つまり、その分コストも増加する。
また、NFTを正しく理解した判決が出るかどうかもわからない。
「ガス代」が高騰している

NFTなどブロックチェーンを処理するには「マイナー(採掘者)」と呼ばれる作業者が必要だ。
彼らは記録されるデータが正しいことを承認する作業をしており、これを「マイニング」と呼ぶ。「ガス代」というのは、この「マイニング」に対して支払われる手数料のことだ。
NFTの売買などが行われると、メタデータが書き換わるため、承認作業が発生する。ブロックチェーンは、1秒間に承認できる処理の量が決まっており、上限を超えた場合は処理の優先順位が設定される。この優先順位は、「手数料を多く支払ったもの」から順番に処理される仕組みだ。
そのため、マイニングが少ないときは手数料が安くなり、マイニングが多いときは手数料が高騰してしまう。
現在、ブロックチェーンでは金融系の処理が多く発生しており、ガス代の高騰が目立つ状態だ。これを改善する仕組みの導入が予定されており、近い将来、改善される可能性はある。しかし、現状では高額すぎると感じても仕方ないだろう。
NFTデータの価値がなくなる
NFTは、メタデータが紐付いているコンテンツ本体を変更できない仕様になっている。
そのため、コンテンツ本体が何らかの事情で利用できなくなった場合、そのデータの価値はなくなってしまう。
NFTの価値がなくなる例
たとえば、NFT化された「あるサービスのURL」を購入したとする。もし、URL先のコンテンツが削除・変更された場合、紐付いているコンテンツ(ここではURL)を変更できないため、まったく無価値なデータとなってしまう。
NFT化されたデジタルデータを資産として考えた場合、持続性が担保されていないという大きな問題がある。
コンプライアンス基準が未整備である
NFTは資産としての特徴を持つため、消費者トラブルが生じる可能性が高い。
だが、NFTは資金決済法上の暗号資産に該当しないため、NFT事業者は金融規制の監査外となってしまう。つまり、トラブルが起きても自己責任なのだ。
現在、NFTは守るべきコンプライアンス基準が整備されていない。取引をする際は、実際に売買されているものが何であるのかを確認した上で、十分に注意を払う必要がある。
NFTのさまざまな事例

NFTの史上最高額は約6935万ドル(約75億円)
NFTコンテンツで過去最高の落札額は、ビープル(Beeple)のデジタルアート作品「Everydays - The First 5000 Days」で、約6935万ドル(約75億円)という驚異的な値が付いた。
この作品は、2021年2月25日にクリスティーズのオークションへ出品。2週間にわたり入札が繰り返され、最終日には落札の行く末を見守りたいユーザーがサイトに殺到して話題になった。
国内外での活用事例
海外でいち早く成功を収めたのが、プロバスケットボールのNBAが販売した「NBA Top Shot」だろう。
これは、北米男子プロバスケットボールリーグNBAのスーパープレーの動画をデジタルカード化したものだ。レブロン・ジェームズ選手のダンクシュート動画が20万8000ドルで落札されるなど、大きな話題となった。

国内では、音楽業界での活用が話題になった。
2021年6月11日にPerfumeがNFTアート作品「Imaginary Museum “Time Warp”」をリリースした。これは、Perfumeの象徴的なポーズを3Dデータ化したNFTアートだ。なお、このNFTアート作品は、オークションにて約325万円で落札されている。
ゲーム業界もNFTの活用を模索している。
カプコンは2021年2月、「ストリートファイター」のキャラクターをNFTのデジタルトレーディングカードとして発売した。販売した場所は、ゲームアイテムのトレードに特化した「WAXブロックチェーン」だった。

引用元:Twitter
InstagramもNFT参入へ
多くのユーザーが利用しているSNS「Instagram」も、開発者のリークによってNFTへの参入を検討していることが明らかになった。
モバイル開発者であるアレサンドロ・パルッツィ氏が、Instagramの新機能に関するスクリーンショットをTwitterで公開した。
この機能は「Collectibles」と呼ばれ、ユーザーが投稿作成時にその投稿を購入可能なNFTに転換できるというものだ。Collectiblesを設定した投稿はプロフィール内の専用ページに表示され、ほかのユーザーはこの投稿に入札できるという。

その他、日本の代表的なゲームメーカーであるスクウェア・エニックスは、同社のIPである「ミリオンアーサー」を活用したNFTデジタルシールの販売・開発を進めている。
このように、NFTの盛り上がりにともない、NFTマーケットプレイスに参入する企業が増加している。
NFT化を取りやめた事例
逆に、NFTの利用を取りやめた事例もある。
現代美術家の村上隆氏が、同氏の代表的なモチーフである「お花」をドットで描いたデジタルアート作品「108 Earthly Temptations」をNFTマーケットプレイスのOpenSea(オープンシー)に出品していたが、後に取り下げた。
NFTの特性上、NFTを購入したとしても、紐付けられたコンテンツ自体が消失してしまうリスクがある。そうなると、購入者への不利益に直結してしまう恐れがある。
そのため、村上氏は出品を取り下げたと考えられる。なお、村上氏は再度出品する意思があることを公表している。
NFTは資産価値として有効なのか?
デジタルデータは簡単にコピーできるため、絵画や不動産のように現物としての資産価値は認められてこなかった。しかし、NFTによってその状況が変わりつつある。
では、本当にNFTは資産価値として有効なのだろうか?
所有目的なら「本物」を所有することに満足できるか
純粋にコンテンツとして楽しむ場合、唯一無二の「本物」データを所有することで、コレクター欲を満たせるかどうかがポイントになる。そこに価値を見いだせるのであれば、十分に資産価値はあると言えるだろう。
投機目的なら価格や持続性に注意
投機目的の場合、現在はバブルのように価格が高騰しているので、高値でつかまされないように十分な注意が必要だ。
また、前述のようにコンプライアンスが未整備な上、資産価値の持続性が担保されていないという問題もある。
所有権を意識しよう
現在の日本の民法で所有権が認められるのは「有体物」に限られる。そのため、デジタルデータは民法上の所有権の対象にならない。
つまり、NFTはあくまでも単なるデジタルデータであり、NFTに「所有権」は認められていないということになる。
- 相続の対象となるのか
- 高額なNFTの担保設定
- 税務上の取り扱い
このように、NFTデータは法的に整備されていない部分が多い。そのため、絵画や不動産のような「実体のある資産」と同じだと考えないほうがいいだろう。
NFTが取引できるマーケットのまとめ&取引所の口コミ

NFTデータの取引は「NFTマーケットプレイス」で行う
「NFTマーケットプレイス」は、デジタルアートや音楽、ゲームアイテムなど、さまざまなNFTデータを取引するマーケット(取引所)だ。
NFTマーケットプレイスでは、マーケットプレイス内で流通するNFTコンテンツの売買だけでなく、ユーザー自身がNFTを新規発行したり、自分で作成したNFTを販売したりもできる。
NFTマーケットプレイスは日本国内や海外に複数存在している。NFTへの注目が高まってきたため、さまざまな企業が実際に参入したり、参入を計画したりしている。

国内のNFTマーケットプレイスを比較する
国内でNFTマーケットプレイスも運営する暗号資産交換業者は、「Coincheck(コインチェック)」「LINE BITMAX」「GMOコイン」の3社だ。
NFTマーケットプレイスの3社比較
| マーケットプレイス名 | Coincheck NFT(β版) | アダム byGMO | NFTマーケットβ |
| 運営する暗号資産交換事業社 | Coincheck(コインチェック) | GMOコイン | LINE BITMAX |
| 取り扱いアイテム | CryptoSpells(クリプトスペルズ)/The Sandbox(サンドボックス)/NFTトレカ | アートや楽曲、著名なアーティストによる希少性の高いコンテンツ(予定) | Lbgreen/Lbsky/LBblue |
| 決済通貨 | BTC/ETH/LSK/XRP/XEM/LTC/BCH/MONA/XLM/QTUM/BAT/IOST/ENJ | ETH(予定) | LINK |
| サービス開始時期 | 2021年4月 | 2021年8月 | 2021年6月 |
Yahoo! JAPANも参加予定
Yahoo! JAPANが提供するネットオークションサービス「ヤフオク!」が、NFTマーケットプレイスへの参入を発表した。
ブロックチェーンは「LINE Blockchain」を基盤とするため、扱えるNFTアイテムは「LINE BITMAX」と同等になることが予想される。2021年冬から「ヤフオク!」上で取引ができるようになる予定だ。

NFTに対応している仮想通貨を整理・比較する

NFT銘柄とは何か
「NFT銘柄」は、NFTが流通しているブロックチェーンプラットフォームの基軸通貨を指している。他の暗号資産と同様に、暗号資産交換取引所で売買できる。
NFT銘柄は、CoinMarketCapのNFTカテゴリーページで確認できる。確認すればわかるとおり、NFT銘柄は140種類以上も存在する。
だが、多くのNFT銘柄は海外の取引所でのみ売買が可能だ。一部のNFT銘柄のみ、国内の取引所で対応できる。
ここでは、投資家から注目を集めているNFT銘柄を紹介していこう。
チリーズ(CHZ)
チリーズ(CHZ)は、スポーツチームやエンタメ業界でのブロックチェーン活用を目指したプラットフォームで使われる基軸通貨だ。ファントークンとも呼ばれており、ファンビジネスの新しいイノベーションとして注目されている。
ファントークンとは何か
ファントークンとは、ヨーロッパサッカーのクラブチームなど、スポーツクラブが発行する仮想通貨のことだ。これを所有することで、所有することで、クラブが定めた報酬や特別な体験を受けることができる。
チリーズは2019年に上場してから緩やかに推移していたが、2021年2月に入ってから約2ヶ月で価格が15倍以上に値上がりするなど,
高騰している。
現在、国内ではCHZを扱っている取引所はないため、購入するにはバイナンスなどの海外取引所を使う必要がある。ただし、Coincheckとの連携が発表されているので、今後は国内の取引所でも購入できるようになるかもしれない。
フロウ(FLOW)
フロウ(FLOW)は、世界初のブロックチェーンゲーム「CryptoKitties」などをリリースしてきたDapperLabsが開発する新たなブロックチェーンだ。暗号資産には利用者の増加に伴い、スケーラビリティ問題や手数料高騰などの問題が発生しているが、これらの問題点を解消することを目的としたプロジェクトだ。
スケーラビリティ問題とは
スケーラビリティ問題とは、ビットコインのブロックサイズの上限が理由で、ビットコインを送付する手数料が高騰したり、取引の処理が遅延などが発生する問題のことだ。イーサリアムブロックチェーンは、まさにこの問題に直面しており、ガス代の高騰につながっている。
FLOWは、遅延発生の大きな要因となっている承認手続きの処理を改善し、処理速度の高速化を実現した。理論上は従来の数百倍の処理速度を実現できるとしている。
FLOWも国内で扱っている取引所はないため、フォビグローバルなどの海外取引所を使って購入する必要がある。こちらも、Coincheckとの連携はすでに発表されており、チアーズと同様に今後は国内の取引所でも購入できるようになる可能性は高い。
エンジンコイン(ENJ)
エンジンコイン(ENJ)は、シンガポールの企業「Enjin」が運営しているブロックチェーンの「Enjin Platform」で発行されている基軸通貨だ。Enjin Platformはオンランゲーム向けのブロックチェーンで、ゲームアイテムの売買などに用いられることが多い。
エンジンコインマイクロソフトやサムスンといった大企業と提携していることで話題となっている。サムスンのスマートフォン「Galaxy S10」では、仮想通貨ウォレットが内蔵されており、これにエンジンコインにも対応しており注目を集めた。また、マイクロソフトの世界的ゲーム「マインクラフト」にもエンジンコインが組み込まれるなども話題だ。
エンジンコインは大企業との提携などで世界中の投資家から注目を集めており、価格はどんどん高騰している。
国内の取引所では、CoincheckとGMOコインがエンジンコインを取り扱っている。国内の取引所で売買できるので、手を出しやすい銘柄だろう。
サンドボックス(SAND)
サンドボックス(SAND)は、人気のブロックチェーンゲーム「The Sandbox」内で利用できる基軸通貨だ。
スクウェア・エニックスをはじめ、複数の企業やファンドから多額の融資を受けており、大きな期待がされている。
SAND自体は国内で扱っている取引所はないため、購入にはバイナンスなどの海外取引所を使う必要がある。ただし、Coincheckがサンドボックス内の土地「LAND」を取得し、自社のNFTマーケットプレイスで販売を開始している。
パンケーキスワップ(CAKE)
パンケーキスワップ(CAKE)は、「分散型取引所」の基軸通貨だ。分散型取引所とは、ブロックチェーンの「スマートコントラクト」を利用した非中央集権的な取引所のことで、登録が簡単でハッキングリスクが低いという特徴がある。
分散型取引所は、イーサリアムブロックチェーンを採用したものと、BSCを採用したものがあるが、パンケーキスワップは後者を採用している。イーサリアムブロックチェーンはガス代の高騰に頭を悩ませているが、BSCはそのようなことはなく、手数料が安いメリットがある。
現在、国内ではCAKEを扱っている取引所は存在しない。そのため、バイナンスなどの海外取引所を使う必要がある。
NFTの課題
NFTは残されている課題も多い。現在のブームによってバブルのように市場価格がつり上がっている感もあり、バブルが弾けたら一気に熱が冷めてしまう可能性もある。また、コンプライアンス基準が曖昧で、ユーザーの負担や責任が大きすぎる懸念もある。
だが、デジタルデータが日常的に使われている現代では、NFTのような仕組みは必要だ。現在指摘されている課題をクリアすれば、社会インフラの一部としての役割を担うようになっていくだろう。
NFTは我々の生活を変える可能性がある

NFTの果たす役割
この状況を変えたのがNFTだ。デジタルデータを唯一無二なものとしての価値を付加し、履歴の管理がされるようになったことにより、これまで難しかった資産としての価値を持たせることができた。これにより、デジタルデータが「デジタル資産」として流通に乗り、一般の人でも取引ができるようになった。
現在、デジタル資産としてNFTを活用しているのがアートやゲームアイテム、音楽といったジャンルだ。今後はこれだけには留まらず、ライブやスポーツの観戦チケット、コンテンツの特典の権利など、さまざまな用途で活用されるだろう。
デジタルの世界だけでなく、不動産など資産の管理や各種証明書の発行など、リアルなものに対してもNFTが活用されていくことが予想される。